現行の学習指導要領とカリキュラム編成 〜DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-〜
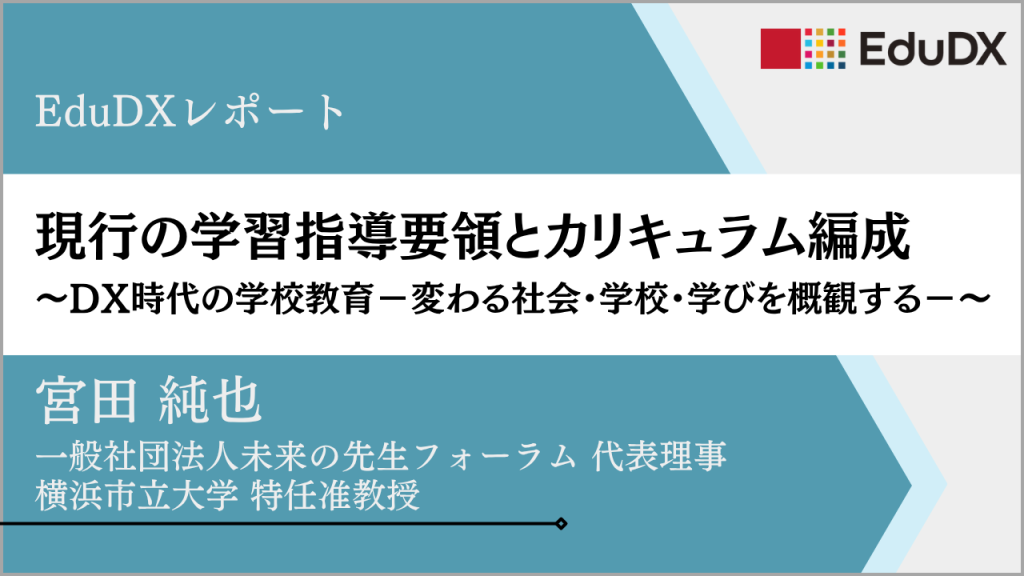
2025年1月31日 宮田 純也(一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事/横浜市立大学 特任准教授)
わが国では学習指導要領に基づいて公教育が展開されている。学習指導要領は学校教育法と同施行規則の規定を基にして、学校ごとに教育課程を編成する際の大綱的基準として文部科学大臣によって定められる国家基準とされている。各学校や教育員会では、この内容を基にして教育内容(カリキュラム)を編成し、教育計画を定めたうえで教育活動を展開する。
公教育自体が教育基本法第1条に「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と定められた目的に向けて運営されているため、先述したように社会が変化すれば資質も変化していくことが推測される。それに伴って学校での教育内容や教育活動も変容していく。
このように、公教育は社会の変化に応じて柔軟に変化することが求められている。そのため、学習指導要領は概ね10年ごとに改訂が行われてきた。この際、カリキュラムの概念についても注目すべき点がある。英語で“curriculum”と表現されるこの用語は、最も一般的な意味として「子どもの学習経験の総体」を指す。すなわち、教科における学びと各種の経験や活動の両方を含む広範な概念である。
このような観点から、教育課程の設計において重要となるのは教科の学びと経験・活動のバランスである。このバランスの取り方は、教育界においてしばしば議論の対象となっている。
学校のカリキュラムには、時間割など計画的に編成された教育内容(顕在的カリキュラム)と、教育者の意図を超えて暗黙のうちに子どもたちに影響を与える教育内容(潜在的カリキュラム)が存在する。これら二つの側面が相互に補完し合い、学校教育の全体構造を形成している。
したがって、学校教育においては単に教科の内容を教授するのみならず、学習環境全体をいかに設計するかが常に問われる。学習指導要領の歴史においても、経験を重視する経験主義と、系統的な知識の習得を重視する系統主義の間で方針が揺れ動いてきた。例えば、2002年から約10年間実施されたいわゆる「ゆとり教育」では、授業数と学習量を削減し、経験主義的なアプローチが強調された。しかし、学力低下への懸念が高まり、社会的な批判が集中した結果、次期改訂では系統主義が再び強化され、授業数と学習量の大幅な増加が図られた。
現在の社会は変化のスピードが増し、複雑化・多様化が進んでいる。このような状況下では、経験主義と系統主義を一律に適用することの限界が指摘されている。教育の重点をどこに置くべきかについては、地域社会や学校の実情に応じて柔軟に決定されるべきである。
このような教育の方向性を踏まえ、中央教育審議会は2016年12月21日に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」と題する答申を公表した。この答申の内容は、2017年の学習指導要領改訂に反映されている。新学習指導要領は、小学校で令和2年度から、中学校で令和3年度から、高等学校で令和6年度から段階的に施行されており、これに基づく教育活動が展開されている。
現代はVUCAと呼ばれる不確実性の高い時代であり、受動的にキャリアを形成することが困難である。むしろ、自らのスキルや能力を活かし、社会に貢献することで実績を積み重ねる能動的な姿勢が求められる。この変化は、静的なキャリア形成から動的なキャリア形成への転換といえるだろう。
このような社会的背景の変化に対応して、現行の学習指導要領でも「何ができるようになるのか」という視点が重視されるようになった。学習指導要領は、知識と技能、思考力や判断力、さらに学びに向かう力の育成を目的としている。これらの要素は、社会で生きて働くための資質・能力を育成するための重要な柱となっている。
また、教育の視点はコンテンツベースからコンピテンシーベースへと転換している。コンピテンシーとは、単なる知識や技能の習得にとどまらず、それらをいかに活用するかという思考や行動を含む概念である。この考え方は、OECDの”Future of Education and Skills 2030”プロジェクトで提唱された”Learning Compass”にも取り入れられており、世界的な教育の潮流となっている。
現行の学習指導要領では、資質・能力の育成を次の3つの柱に基づいて推進している。すなわち、「生きて働く知識及び技能」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等」、そして「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性等」である。このような資質・能力を育成するためには、従来の学び方から脱却し、「主体的・対話的で深い学び」への転換が不可欠である。これは、自ら課題を設定し、多様な価値観を持つ他者との対話を通じて視野を広げ、課題解決に向けた行動を実践する学びの在り方である。この学びは、受動型・暗記中心の教育から能動型・思考中心の教育への転換を象徴している。
こうした指針に基づき、教育現場ではカリキュラム・マネジメント[1]と主体的・対話的で深い学び[2]を両輪として、継続的かつ計画的に授業改善を図ることが求められている。この取り組みは、未来の社会を支える人材の育成に向けた重要な一歩であり、社会の変化に即応する教育の鍵となるものである。 そのほかにも「探究学習」という教育方法が学校での教育活動における中核的存在となり、教育方法が大きく変わろうとしている。次節で詳しく取り上げる。
[1] カリキュラム・マネジメントとは、学校教育の目標達成に向けて、教育課程を計画・実施・評価し、改善する一連のプロセスを指す。これにより、教育内容と方法、指導体制、資源活用の調整が図られることになる。各教科・領域の連携を強化し、学校全体で一貫した学びを提供することで、生徒の学びの質の向上を目指す。
[2] 主体的・対話的で深い学びは、児童生徒が能動的に学びに取り組み、他者との対話を通じて思考を深める学習方法である。自ら課題を見つけ、考え、表現し、解決する力を育成できるため、21世紀型スキルの育成を視野に、探究的で協働的な活動を重視し、生涯にわたり活用可能な知識・技能の定着を目指すものである。
参考文献:
・安彦忠彦. (2006). 『改訂版教育課程編成論』. 放送大学教育振興会.
・OECD. (n.d.). ”Future of Education and Skills 2030”.
https://www.oecd.org/en/about/projects/future-of-education-and-skills-2030.html
a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/24/1397727_001.pdf
・宮田純也 著. (2025). 『教育ビジネス』. クロスメディア・パブリッシング.
・宮田純也 編著. (2023). 『SCHOOL SHIFT』. 明治図書.
・宮田純也 編著. (2024). 『SCHOOL SHIFT2』. 明治図書.
・リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著、宮田純也 監修. (2023). 『16歳からのライフ・シフト』. 東洋経済新報社.
