新型コロナウイルスが学校教育に与えたインパクト-令和の日本型学校教育-〜DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-〜
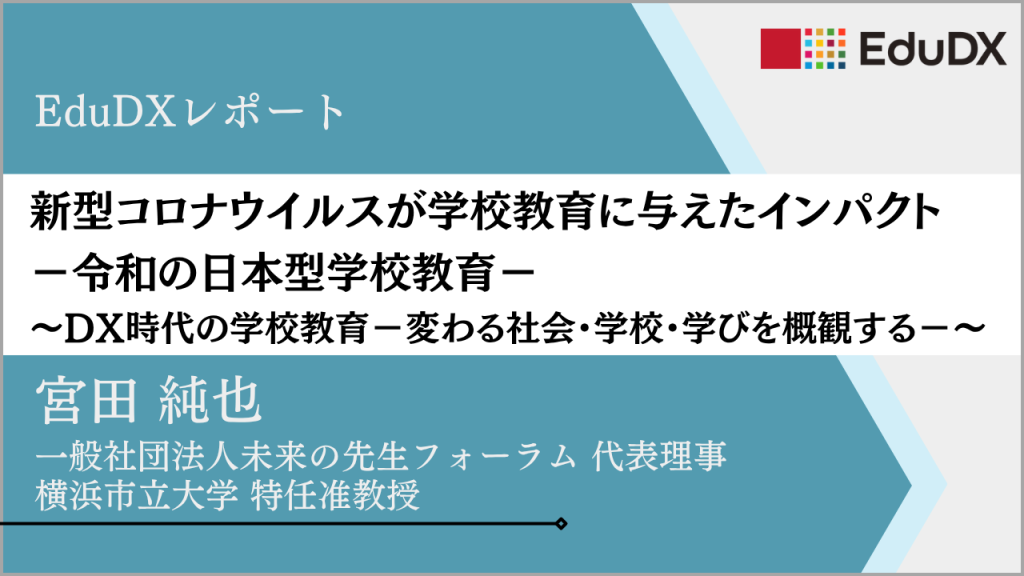
2025年1月31日 宮田 純也(一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事/横浜市立大学 特任准教授)
2021年1月には中央教育審議会が「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~」という答申を発表した。この答申では、従来の日本の学校教育を現代の状況に適応させるため、個別最適な学びと協働的な学びを統合し、一体的に充実させることが新たに目指された。着目すべき点は、2017年改訂の学習指導要領を新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが発表された2020年3月11日以降の社会状況を踏まえて更新を図った点である。新型コロナのパンデミックが公教育に与えたインパクトは広範に及んでいるが、GIGA(Global Innovation Gateway for All)スクール構想が前倒しで実施されたことにより、情報インフラ基盤が公教育に整備された点がDXという観点では特筆される事象である。
この事業は単なる学校教育のデジタル化にとどまらず、公立学校において一人一台端末・高速ネットワーク・クラウド環境が整備され、学校をだれ一人取り残すことなくグローバルに開いていくことを目指すDX化に近い取り組みと言える。
GIGAスクール構想の実施により、ICTは教育現場において従来の補助的なツールという役割を超え、学習を支える不可欠な要素へと変容しつつある。この構想のもと、生徒はICTを活用してリアルタイムで情報を共有し、議論を重ねながら学習を進めることが可能となった。これにより、学びの深さおよび広がりが飛躍的に向上し、従来の教員による一方向的な知識伝達モデルから、双方向性と協働性を特徴とする新たな学習形態への転換が進んでいる。
さらに、ICTの導入は学習形態の変革および教育の質の向上に寄与するだけでなく、生徒が主体的かつ能動的に学び、他者と協働するための環境を整備している。このような環境においては、学習の効率化と個別最適化が促進され、学校教育の在り方そのものに構造的な変化が生じつつある。教育現場へのテクノロジーの浸透は、コンピテンシーベースの学習を実現するための重要な基盤を形成し、学びの深化と多様化を一層推進するものである。
このように、COVID-19のパンデミックを契機として、学校教育のIT化が急速に進展し、学習形態は大きな変容を遂げた。GIGAスクール構想およびEdTechを活用した新たな教育モデルの普及により、教育現場における指導方法と学習の質は著しく高度化し、教育のあり方そのものが進化を遂げている。このような変化は、学習者の主体性や協働的思考を育むと同時に、将来の社会に必要とされる資質・能力の育成に資するものである。
そこで、上述した答申においては個別最適な学びと協働的な学びを統合し、一体的に充実させることが目指された。
個別最適な学びとは、各生徒が自分のペースで学びを進め、試行錯誤を重ねながら学びを深めていくことを意味する一方、協働的な学びは他者と協力し、互いに学び合うことで、個人では得られない知見を得ることを指す。
生徒一人ひとりの多様な学習ニーズに応えつつ、社会的な協働力を育成することを目指した学びの在り方を示している。
まず、個別最適な学びとは、学習者の興味・関心、能力、学習進度に応じて柔軟に学習内容や方法を調整し、各自に適した学びを提供するものである。この概念には、「指導の個別化」と「学習の個性化」という二つの側面が含まれる。指導の個別化とは、学習者の理解度や習熟度に基づき、適切な指導や支援を行うことであり、ICTを活用したアダプティブ・ラーニングがその代表例である。この技術により、リアルタイムで学習者の進捗に応じた課題提示やフィードバックが可能となり、学習の効率化と効果的な知識の定着が期待される。一方、学習の個性化とは、学習者が自らの興味や将来のキャリアビジョンに基づいて学習課題や方法を選択し、主体的に学びを深めることである。これを支える方法の一つとして、eポートフォリオが挙げられる。学習者は自身の学習プロセスを振り返り、改善点を特定しながら学びの質を高めることができる。
次に、協働的な学びは、他者との相互作用を通じて共通の課題に取り組み、より深い理解と創造的な解決策を見いだす学習形態である。異なる背景や視点を持つ者同士が協働することで、批判的思考力や社会的スキル、コミュニケーション能力の育成が促進される。この学びの実践例として、探究学習やプロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)が挙げられる。これらの手法では、学習者がグループ活動を通じて情報収集、分析、成果の発表までを行うことで、学びのプロセス全体にわたる協働が実現される。教員の役割も従来の知識伝達者から、学びを支援し、学習者間の協働を促進するファシリテーターへと変化している。また、ICTの導入により、地理的制約を超えた協働の機会が提供され、多様な学びの可能性が広がっている。
個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させることは、現代の教育において不可欠である。学習者が個別学習で培った知識やスキルを協働の場で共有し、他者の視点を取り入れながら新たな洞察を得ることが、学びの質を一層高める鍵となる。たとえば、授業の前半で個別学習を行い、後半でグループディスカッションを実施することで、各自の学びを総合化し、発展させることが可能である。また、学びの可視化ツールを用いることで、学習者は自らの進捗を振り返り、他者との協働を通じて得た成果を再確認できる。このような統合的アプローチを実現するためには、教員が学びの設計者として、個別最適と協働的な学びを組み合わせた教育活動を意図的に計画することが求められる。
このように、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実は、子どもの主体的で対話的な深い学びを促進し、21世紀型スキルの涵養に資するものである。2024年12月25日に文部科学大臣から中央教育審議会へ学習指導要領の改訂について諮問があったが、次期学習指導要領においてもこのような概念や方向性は維持されると推測している。
参考文献:
・中央教育審議会.(2021).『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)』https://www.mext.go.jp/content/20210126-mxt_syoto02-000012321_2-4.pdf
・宮田純也 著. (2025). 『教育ビジネス』. クロスメディア・パブリッシング.
・宮田純也 編著. (2023). 『SCHOOL SHIFT』. 明治図書.
・宮田純也 編著. (2024). 『SCHOOL SHIFT2』. 明治図書.
・リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著、宮田純也 監修. (2023). 『16歳からのライフ・シフト』. 東洋経済新報社.
