人生100年時代に求められる資質能力とは
〜DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-〜
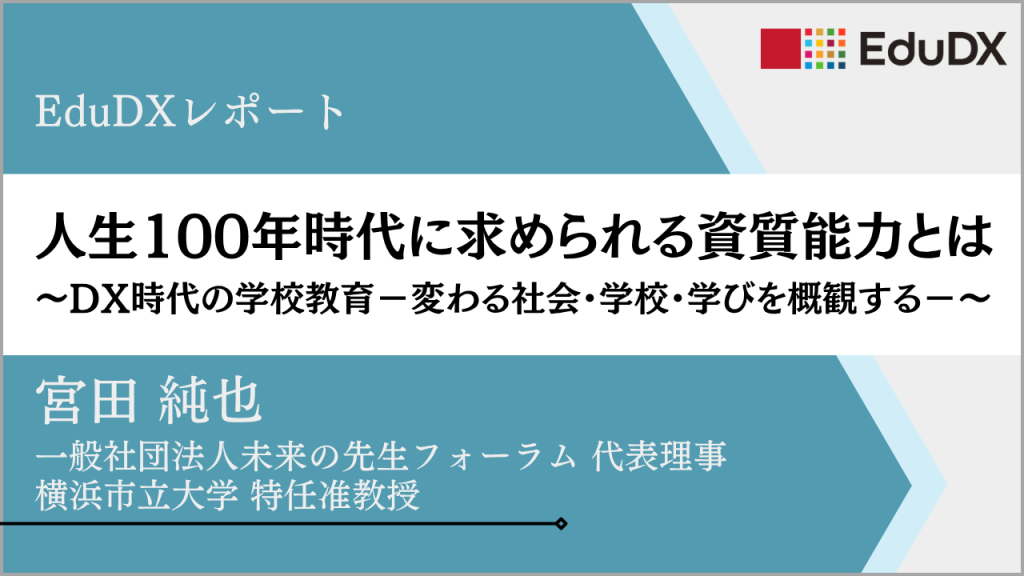
2025年1月31日 宮田 純也(一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事/横浜市立大学 特任准教授)
「人の時代」という場合の「人」とはどのような特徴を持っているのだろうか。機械と比較しながら考察していく。
まず、大前提として「人の時代」は「機械の時代」に重要とされた知識を土台に展開されるなど、「機械の時代」を土台として高度化しているという点である。つまり、かつての時代に必要とされたものが不要となったのではなく、相対的に価値が下がり、より高度なものが必要になったという点に留意しなければならない。
知識基盤社会(knowledge-based society)では、知識の土台の上にあるのは知恵だと私は考えている。ということは、土台である知識をないがしろにしてはならない。あくまで知識を土台にして知恵を創造していくことになるからである。知恵というのは、今までの人生の経験を踏まえて、知識に価値観、思考、行動、省察を掛け合わせることで生まれるものである。知識を高度化すると知恵になるとも言えるだろう。
今日は人類の歴史の中でも特筆すべき時代であり、個人がこれまでにない大きな力を持つ時代だと前回で述べたが、知恵の活用が情報通信技術によって経済を動かす資本の役割を担うようになったからだと考えられる。つまり、「人の時代」における資本というのは資金や不動産、有価証券だけではない。私たち人が持つ知恵は柔軟性があり、流動的であり、常に拡張し転換可能な資本なのである。経済活動の中心が機械ではなく私たちに移っていると言えよう。それは近年のスタートアップなどの興隆を見れば良く理解できる。
情報通信技術の進展を梃子として、個々の能力が拡張され、知識を活用して知恵を創造し、グローバルな情報の受発信が可能となった結果、起業などの経済活動が容易になり、知恵の総体的な経済価値が上昇している。
情報通信技術の重要性を理解するには、グローバル化の歴史的展開を振り返る必要がある。グローバル化は、15世紀半ばの「大航海時代」に端を発している。この時代は、スペイン女王イサベルによるコロンブスへの支援に象徴されるように、国家が主導的役割を果たした時代であった。当時の遠洋航海には膨大な資金が必要であったためである。その後、産業革命が起こると、民間に資本が蓄積され、企業、特に多国籍企業が主役となった。そして21世紀においては、情報革命の到来により、個人が主導する時代へと移行したのである。
情報通信技術の進展により、シェアリングエコノミーやギグワークといった新しい働き方が普及し、ビジネス活動の細分化が促進されるとともに、起業や独立にかかるコストも著しく低下している。この結果、資本の有無にかかわらず、個人の発想や強みを活かして新たなサービスや仕事を創出し、さらには新たな産業を構築することも可能となった。一例として、個人のYouTuberやインフルエンサーが大手メディアを凌ぐ社会的インパクトを持つケースが挙げられる。このように、自らの努力次第で生き方や働き方を選択可能な時代が到来したといえよう。
このような変化の激しい、予測困難な時代において、人々が養うべきものは知恵以外に何であろうか。先述したように工業社会が「機械の時代」であったのに対し、情報社会は「人の時代」である。「人」が持つ特性として、創造性や感情、批判的思考が挙げられる。これらは機械には代替不可能なものであり、今日に世間を騒がせている生成AIでも今のところ代替は難しいとされている。上述した人が持つ特性は今後の社会においてますます重要性を増すであろう。
リンダ・グラットンとアンドリュー・スコットの著書『16歳からのライフ・シフト』(宮田純也監修、東洋経済新報社)を参考にすると、明治から昭和にかけての人生設計は、教育・仕事・引退という3ステージ制に基づく「ベルトコンベア型の人生」と呼べる。この時代は、人口増加と経済成長が右肩上がりで進み、「良い学校」から「良い会社」への移行が人生の成功モデルとして共有されていた。
一方、情報革命による変化は産業構造にとどまらず、人生設計にも「ゲームチェンジ」をもたらした。これにより、人生は複数のフェーズやステージを経る「マルチステージ型」に変容した。静的な人生から動的な人生への転換が進み、個々の働きかけによって多様なチャンスが生まれる自由な社会が形成されている。
この新たな時代においては、3ステージ型の「教育」フェーズで身に付けた限られた専門技能だけでは対応が難しい。マルチステージ型の人生では、移行を繰り返す中で独自性が高まり、その都度「学び直し」が求められる。生涯を通じて学び続け、自己を更新する能力が重要であり、具体的には創造性、深い理解、自発性、集合的知性、批判的思考が鍵となる。このような力を養うことで、個人が多様な社会変化に適応し、自律的に人生を構築できるようになるのである。つまり、学びというのは再創造のプロセスだと考えられる。
知恵を始めとした新たな資質能力の獲得に教育という営みは大きな役割を担う必要がある。そのためには学び自体も変わっていくことになるだろう。学校教育も変化しようとしている。そこで、次回では学校教育での学びの変化について考察する。
参考文献:
・宮田純也 著. (2025). 『教育ビジネス』. クロスメディア・パブリッシング.
・宮田純也 編著. (2023). 『SCHOOL SHIFT』. 明治図書.
・宮田純也 編著. (2024). 『SCHOOL SHIFT2』. 明治図書.
・リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著、宮田純也 監修. (2023). 『16歳からのライフ・シフト』. 東洋経済新報社.
