VUCA・人生100年時代
〜DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-〜
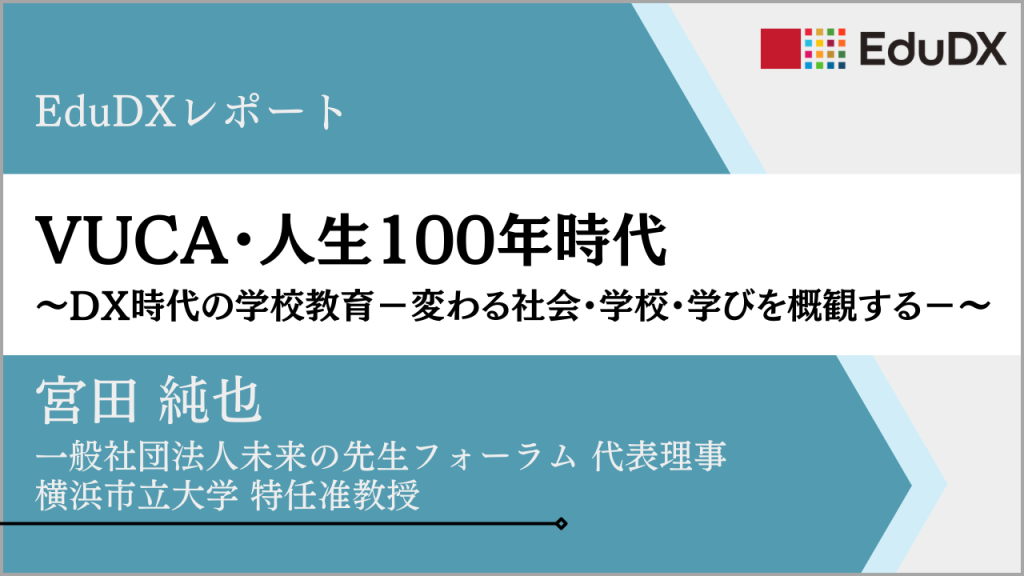
2025年1月31日 宮田 純也(一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事/横浜市立大学 特任准教授)
本連載では「DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-」をテーマに全12回にわたって今日起こっている社会構造の変化と、それに伴う学校教育と学びの変容について、全体像を概観することを試みる。なお、全12回のタイトルは以下のとおりである。
①VUCA・人生100年時代
②VUCA・人生100年時代と学校教育
③人生100年時代に求められる資質・能力とは
④現行の学習指導要領
⑤探究学習とは
⑥新型コロナウイルスが学校教育に与えたインパクト-令和の日本型学校教育-
⑦OECD Learning Compass 2030から考える国際的な学校教育改革のトレンドと日本
⑧第4期教育振興基本計画:持続可能な社会の創り手へ
⑨DX化が進む学校教育-工業型から情報型への転換-
⑩AI時代の学校教育の形
⑪これからの教員の在り方
⑫未来の先生フォーラムが実現を目指す学校教育のSHIFT
それでは第1回の内容に移りたい。今日の社会は以下の4つが特徴として挙げられる。
①高度情報社会
情報通信機器や技術の発展により、情報の流通量が爆発的に増えている。情報は地理的な制約を乗り越えてリアルタイムでグローバルに流通するため、情報の受発信が高速化することで社会が高速化する。これによって社会の変化も高速化することが推測される。
また、従来のようにマスメディアなど情報発信者が限られることはなく、私たち自身がSNSなどで情報を発信することができる情報の発信者という側面を持つようになり、インフルエンサーなどの新たな職業が生まれている。さらに情報の受発信が活性化するだけでなく、今後は生成AIにより情報が情報を生み出すという情報の自己生成によって、さらに情報量が増加することが推測される。
②知識基盤社会、多文化共生社会
爆発的に増える情報の流通のみならず、人の往来や交流も活性化し、文化が重層的に重なる。これにより、様々な新たなことが創発的により生み出される。結果として社会は高度化を遂げ、大量に流通する情報は価値が低くなると共に知識自体の価値も下がることになる。知識基盤社会は知識を土台にする社会と解釈されるが、知識の上にあるものは知恵だと考える。つまり、知識を活用して知恵を創るというように私たちが求められる行動も高度になるのではないだろうか。
③人生100年時代
『16歳からのライフ・シフト』(東洋経済新報社)において記述されているように日本の2007年生まれの半数が107歳まで生きるという長寿の時代が到来することで、いろいろなライフイベント・社会変化がより多く起こることが推測される。これにより、一斉進行型の人生(教育・仕事・老後という3ステージ型)から多様な人生(様々なフェーズやステージへの「移行(トランジション)」が発生するマルチステージ型)という人生の複雑化が進行する。
④グローバル社会
グローバル化というのは1492年の大航海時代から開始されたものであり、3つのフェーズに分けられる。1492年から1800年ごろまでの「国家のグローバル化」、そして2000年ごろまでの「企業のグローバル化」、そして今に至るまでの「個人のグローバル化」である。個人のグローバル化は①の高度情報社会の到来が主因とされるが、工業技術と企業の発展によってLCCなどの安価な移動手段が普及することにより、物理的な移動も容易になることでグローバル化が促進されている。これにより多文化共生などの課題が我が国をはじめ多くの国で発生している。
このような変化を総称して今日は「VUCA時代」と呼ばれている。
VUCA時代とは、
・Volatility(変動性)
・Uncertainty(不確実性)
・Complexity(複雑性)
・Ambiguity(曖昧性)
の略であり、「変化の激しい予測困難な時代」という意味で今日ではよく使われている。
このような時代になったのは、我が国においては90年代に起こったと言われる「情報革命」が主因である。
ゲームチェンジャーとしてのテクノロジー、情報通信技術が台頭することにより、私たちの社会は上述した4つの社会的特徴を持つようになったと言われる。「知識」を活用して「知恵」を創造し、様々な情報をグローバルに受発信する主体に一人一人が変化する時代の到来である。つまり、歴史的に見て私たち一人一人の力が最も高い時代と考えられる。
人生100年時代で寿命が延びると、社会保障制度など今までの人口増・右肩上がりの経済成長が前提とされる社会・経済システムを再考する必要がある。企業の平均寿命も人間の寿命よりもはるかに短くなっているため、個人のキャリア形成やライフデザインも複雑化・複線化していくことになるだろう。その時、自分にとって適切な先行事例は存在せず、自律的にキャリアや人生を設計する必要が生じる。考え、行動し続けながら人生を歩むことになるため、暗夜を行くような状況に置かれる人が増えていくことが推測される。
つまり、「良い」ということが多義化する時代とも言え、自ら定義しなければならない。かつてのような「良い」学校に入って「良い」会社というような一般的な「良い」というリオタールが『ポスト・モダンの条件』(1989)で述べた「大きな物語(近代社会がそれ特有の世界観と人間観によって社会・文化的コンテキストを維持・正当化するための物語)」は終焉しつつあるのではないだろうか。
そんな時代では福沢諭吉が『学問のすすめ』で主張した「心身の独立」の重要性がより高まるだろう。心の独立とは精神的な独立、つまりアイデンティティの確立、身の独立とは経済的な独立、つまり職業人としての独立と解釈できる。
教育の目的の一つが人間の自己実現に資するものであるとすれば、社会が変わっている中で自己実現の困難さは増している。それに伴い、今日はより一層、教育という営みの果たす役割や社会的期待は増すばかりであろう。
次章では近代学校教育に焦点を当て、その成り立ちや社会的役割について概観し、今日とこれからの学校教育を考察するにあたっての問題提起を試みる。
参考文献:
・宮田純也 編著. (2023). 『SCHOOL SHIFT』. 明治図書.
・宮田純也 編著. (2024). 『SCHOOL SHIFT 2』. 明治図書.
・ジャン=フランソワ・リオタール 著、小林康夫 訳. (1989). 『ポスト・モダンの条件: 知・社会・言語ゲーム』. 水声社. ・リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著、宮田純也 監修. (2023). 『16歳からのライフ・シフト』. 東洋経済新報社.
